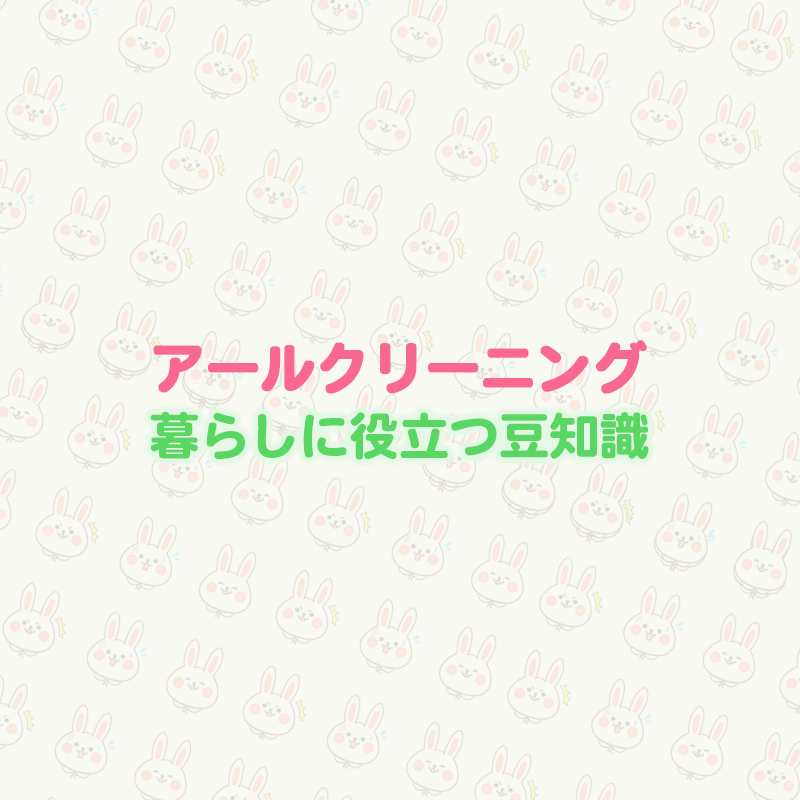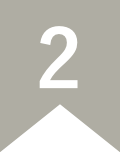お風呂場は湿気が多くカビが発生しやすい場所のため、日々の掃除だけではカビの発生を完全に防ぐことが難しい場合もあります。
そのため、効果的な対策を知り、適切に実践することが重要です。
この記事では、お風呂のカビの原因から、予防法、取り除く方法までを徹底的に解説します。
カビが発生する原因は湿度と換気不足

お風呂のカビは、湿気と温度が高い環境で発生しやすく、特に浴室内の換気が不十分な場合に問題となります。
カビは、湿度、温度、栄養源がそろうことで繁殖しやすくなり、放置すると壁や天井、ゴムパッキンの隙間などに根を張り、簡単には落とせなくなります。
お風呂のカビが発生する主な原因には、以下のような要因があります。
湿度と温度の高さ
浴室はお湯を使用するため、湿度が常に高く、さらに温かい環境がカビの繁殖を促進します。
特に気温20~30℃、湿度70%以上の環境では、カビが活発に増殖すると言われています。
換気不足
入浴後に換気をしない、または換気扇の使用時間が短いと、湿気がこもりやすくなります。
特に窓がない浴室や、密閉性の高い住宅では、換気が不十分になりがちです。
換気扇を回していても、浴室の隅や床に湿気がたまり、カビが発生することもあります。
汚れや残留水分
石けんカス、皮脂汚れ、シャンプーの残りなどが浴室内に付着し、それがカビの栄養源となります。
また、シャワー後や浴槽使用後に壁や床に水滴が残ったままだと、カビが根を張りやすくなります。
特に、目地やゴムパッキン部分にたまった水分はカビの温床になりやすいです。
使用頻度が高い
家族の人数が多い家庭では、お風呂の使用回数が増え、湿気がこもる時間が長くなるため、カビが発生しやすくなります。
特に長時間お湯をためることが多い場合は、浴室内の温度と湿度が高い状態が続くため注意が必要です。
掃除の頻度が低い
定期的に掃除をしていないと、カビの原因となる汚れが蓄積し、発生しやすくなります。
特に目立ちにくい天井や換気扇周り、シャワーヘッドの裏などは掃除が行き届かず、気づいたときにはカビが広がっていることもあります。
これらの原因を把握し、適切な対策を講じることで、カビの発生を未然に防ぐことができます。
次の章では、カビを防ぐための具体的な方法について詳しく解説していきます。
お風呂(浴室)のカビ予防法

お風呂のカビを予防するためには、日々のちょっとした工夫が重要です。
以下の方法を取り入れることで、カビの発生を防ぐことができます。
- 換気を徹底する: 入浴後は必ず換気扇を回し、浴室の湿気を外に逃がしましょう。
また、窓を開けることでも効果的です。 - シャワー後に水滴を拭き取る: シャワー後に浴槽や壁、鏡に残った水滴を拭き取ることで、カビの栄養源を減らすことができます。
- カビ防止グッズを使用する: 市販のカビ防止スプレーやカビ取りシートを使用することで、カビの発生を抑えることができます。
- 定期的な掃除: 定期的に浴室の掃除を行い、汚れやせっけんカスを取り除くことでカビの発生を予防できます。
これらの予防法を実践することで、カビの発生を抑え、清潔な浴室を維持することができます。
カビを取り除く清掃方法3選

お風呂のカビは放置するとどんどん広がり、見た目が悪くなるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、早めの対処が重要です。
以下では、自分でできる効果的なカビ取り方法を紹介します。
1. 市販のカビ取り剤を使用
市販のカビ取り剤は、手軽で効果的なカビ除去方法です。
スプレータイプやジェルタイプなど、種類によって使い方が異なりますが、スプレータイプが特に便利です。
カビが発生している部分に薬剤をたっぷり吹きかけ、パッケージの指示通りに一定時間放置することで、カビが分解され、簡単に除去できます。
強力な成分が含まれているため、頑固なカビにも効果がありますが、使用時には換気を十分に行い、ゴム手袋やマスクを着用することをお勧めします。
これにより、安全にカビ取りを行うことができます。
2. 重曹と酢を使ったカビ取り
重曹と酢を使ったカビ取り方法は、環境にも優しく、経済的です。
重曹はカビの汚れを吸着し、酢はカビを分解します。
まず、カビの発生した場所に重曹を振りかけ、その上から酢をスプレーします。
酢と重曹が反応して泡立ち、カビを浮かせてくれるため、数分間放置した後、スポンジやブラシでこすり洗いを行い、カビを落とします。
頑固なカビの場合は、数回繰り返すことが必要です。
酢は無害で敏感肌の方にも安心して使えますが、使用後は水でしっかりと洗い流してください。
酢の匂いが残ることがありますが、時間とともに消えるので心配いりません。
3. 目地や隅のカビには歯ブラシを活用
お風呂のカビは、特に目地や隅など、細かい部分に発生しやすいです。
こういった狭い場所にカビが生えると、掃除がしにくく、放置するとさらにカビが繁殖してしまいます。
目地や隅のカビを効率よく取り除くためには、歯ブラシを活用するのが効果的です。
まず、目地にカビ取り剤を吹きかけて数分間放置します。
その後、歯ブラシを使って優しくこすり、目地の中に入り込んだカビを取り除きます。
歯ブラシの毛先が細かい部分にも届くため、隅々まできれいに掃除できます。
また、歯ブラシを使うことで、傷をつけることなく丁寧にカビを除去できます。
もしカビが根深く残っている場合、重曹や酢と組み合わせて使用することで、より効果的にカビを取り除くことができます。
目地のカビ取りは根気が必要ですが、こまめに掃除をすることで再発を防ぐことができます。
これらの方法でカビを取り除くことができますが、場合によってはカビが頑固で、完全に取り除けないことがあります。
また、カビが見えない部分にも潜んでいる可能性があるため、全体的にしっかりと掃除をすることが重要です。
無理に自分で取りきれない場合や、カビが広がりすぎて手に負えない場合は、プロのカビ取り業者に依頼することをおすすめします。
プロの業者は、専用の機材や薬剤を使って、短時間で効率的にカビを取り除いてくれるため、安全で安心です。
カビを根本から取り除くならプロに依頼

カビ取りをプロの業者に依頼することで、時間と労力を大幅に削減できます。
特に、目に見えないところに生えているカビや、頑固にこびりついたカビには専門的な技術と道具が必要です。
- 徹底的な清掃: プロの業者は専用の機器や薬剤を使用し、隅々まで徹底的に掃除します。
- カビの再発防止: プロはカビの発生原因を特定し、適切な対策を講じて再発を防ぎます。
- 安全で効率的: 市販のカビ取り剤では手が届かない場所も、プロが適切に対応します。
特に、カビがひどくなってしまっている場合や、自分では手に負えないと感じた場合は、専門業者に依頼するのが一番です。
浴室清掃はアールクリーニングへお任せください!

アールクリーニングは最新の洗浄機器、ならびに技術とアフターサービスで、多くのお客様にリピートをいただいております。
以下では、アールクリーニングの強みを紹介します。
1.高い技術力と徹底した品質管理

アールクリーニングの作業実績は50万件以上!
その中でも浴室のクリーニングは人気のメニューです。
アールクリーニングでは、独自の研修制度を導入しています。
社内に専用の研修施設を設け、さまざまなメーカーのエアコンや換気扇、水回り設備を実際に使って練習できる環境を整備。
厳しい研修を最後までクリアしたスタッフだけが、現場に出ています。
「どのスタッフに当たっても品質が一定」
という安心感があるのは、この徹底した教育体制があるからこそです。
2.豊富な実績と安心のサポート体制

アールクリーニングの累計作業実績は、50万件以上!
その中でも浴室クリーニングは特に人気のメニューで、多くのお客様から高い評価をいただいています。
実際にいただいた Google口コミは1,100件を突破し、満足度の高さが数字としても証明されています。
さらに、作業後には 2週間の保証期間を設けており、万が一気になる点があった場合も迅速に対応
初めての方でもリピートの方でも、安心してご利用いただける体制を整えています。
3.リーズナブルな価格設定
「プロの掃除は高いのでは?」と感じる方もご安心ください。
アールクリーニングは本社を郊外に構え、賃料や駐車場代などの余計な経費を徹底的に削減。
その分をサービス価格に反映し、一般的な相場よりもリーズナブルにご利用いただけるよう努めています。
「一度だけ」ではなく「またお願いしたい」と思っていただける価格帯を実現しているのも、アールクリーニングの強みです。
体験しませんか?
アールクリーニングの対応地域一覧
アールクリーニングでは下記の地域でご依頼を承っております。
お住まいのエリアが対象かどうか気になる方は、以下から開いて一度チェックしてみてください。
開いて対応地域を詳しく見る
※以下の各ページではエアコンクリーニングについてご紹介していますが、ハウスクリーニング全般もお電話やメールからご相談を承っております。
東京都
23区全域
千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区
市部
八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 武蔵村山市 / 多摩市 / 稲城市 / 羽村市 / あきる野市 / 西東京市 / 瑞穂町(西多摩郡) / 日の出町(西多摩郡)
埼玉県
さいたま市全域
緑区 / 西区 / 浦和区 / 桜区 / 中央区 / 南区 / 大宮区 / 北区 / 見沼区 /
その他の市町村
川越市 / 川口市 / 所沢市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / 蓮田市 / 吉川市 / ふじみ野市 / 白岡市 / 三芳町(入間郡) / 松伏町(北葛飾郡)
神奈川県
横浜市
鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ケ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 緑区 / 青葉区 / 都筑区 / 港南区 / 旭区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 戸塚区
川崎市全域
川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 宮前区 / 多摩区 / 麻生区
その他の市区・郡部
相模原市緑区 / 相模原市中央区 / 相模原市南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 秦野市 / 厚木市 / 大和市 / 伊勢原市 / 海老名市 / 座間市 / 綾瀬市 / 葉山町(三浦郡) / 寒川町(高座郡) / 愛川町(愛甲郡) / 清川村(愛甲郡)
よくある質問(Q&A)
Q1. お風呂のカビはなぜすぐに生えてしまうのですか?
A. お風呂はカビにとって理想的な環境です。
湿度・温度・皮脂汚れの3つがそろうため、掃除後でも数日で再びカビが発生することがあります。
入浴後の換気と水滴の除去を習慣にすることで、発生を大幅に抑えられます。
Q2. 黒カビとピンク汚れは同じものですか?
A. 違います。
ピンク汚れは「ロドトルラ」という酵母菌で、カビではありません。
ただし放置すると黒カビの温床になります。
見つけたら早めに中性洗剤で落としましょう。
Q3. カビ取り剤と漂白剤の違いはありますか?
A. 市販のカビ取り剤は「塩素系漂白剤」が主成分です。
黒カビの色素まで分解できるため効果が高いですが、刺激も強めです。
素材がデリケートな場所には酸素系漂白剤(塩素不使用タイプ)を使うと安心です。
Q4. 重曹やクエン酸でもカビは落とせますか?
A. 軽度のカビなら落とせます。
皮脂や石けんカスを重曹で分解し、仕上げにクエン酸で水垢を中和させると効果的です。
ただし黒カビのように根が深い汚れは、塩素系カビ取り剤でないと完全に除去できません。
Q5. カビ取り剤を使うときの注意点は?
A. 必ず換気をし、マスク・手袋を着用してください。
カビ取り剤を広範囲に使う場合は、目や肌を保護するゴーグルも有効です。
また、酸性洗剤(クエン酸など)と混ぜると有毒ガスが発生するため、絶対に併用しないようにしましょう。
Q6. カビ取りのベストタイミングはいつですか?
A. 湿度が低い「午前中」や「入浴後すぐ以外の時間帯」が最適です。
カビ取り剤は乾いた状態の方が効果を発揮しやすいため、壁や床の水気を軽く拭き取ってから作業しましょう。
Q7. パッキンの黒カビはどうすれば落ちますか?
A. カビ取り剤を塗布し、キッチンペーパーで覆って30分〜1時間ほど置くと効果的です。
その後に水で洗い流し、しっかり乾燥させてください。
長年染みついた黒ずみは、素材の内部に根が残っているため、完全に落とすのが難しいこともあります。
Q8. 天井や換気扇のカビ取りは自分でできますか?
A. 天井や換気扇のカビは、作業中に胞子が落ちて広がるおそれがあるため、注意が必要です。
自分で行う場合はマスクとゴーグルを着用し、漂白剤が垂れないようにモップなどに布を巻いて拭き取りましょう。
心配な場合はプロに依頼するのが安心です。
Q9. お風呂のカビを防ぐための習慣はありますか?
A. 入浴後に「冷水シャワーで壁や床の温度を下げる」「浴室全体をタオルで軽く拭き取る」「換気扇を2〜3時間まわす」などを習慣にすると、カビが生えにくくなります。
カビの発生を抑える防カビくん煙剤も定期的に使うと効果的です。
Q10. 自分で掃除してもカビが取れない場合は?
A. カビがパッキン内部や目地の奥まで入り込んでいる可能性があります。
無理にこすると素材を傷めてしまうため、プロのクリーニング業者に依頼しましょう。
専用の洗剤と高圧洗浄で、根元からしっかり除去してもらえます。
まとめ
お風呂のカビは、湿気や換気不足などが原因で発生しやすく、放置するとどんどん広がってしまいます。
しかし、日々の予防や掃除をしっかり行うことで、カビの発生を抑えることが可能です。
もし、カビ取りが難しくなってきた場合は、プロの業者に依頼することで、確実に解決できます。
アールクリーニングの「風呂・浴室クリーニング」では、専用の道具と技術で、頑固なカビも徹底的に除去します。
忙しい方や、カビの取り方に悩んでいる方は、ぜひ一度プロに相談してみてください。
清潔で快適なお風呂を維持するために、今すぐカビ対策を始めましょう。