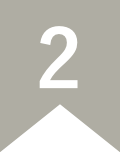押し入れを開けたときにカビのニオイや黒ずみに気づいたことはありませんか?
押し入れは湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい場所の一つです。
本記事では、押し入れにできたカビの対処法、そしてカビ対策に役立つアイテムなどについて詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。
押し入れにできたカビの対処法
 もし押し入れにカビが発生してしまった場合、早めに対処することが重要です。
もし押し入れにカビが発生してしまった場合、早めに対処することが重要です。
ここでは、カビの除去は下記の手順で進めていきましょう。
- 必要な道具を準備する
- 消毒用エタノールで拭き取る
- 乾燥をする
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
1.必要な道具を準備する
押し入れのカビ掃除に必要な以下のものを準備しましょう。
- マスク(防塵・防菌仕様)
- ゴム手袋
- 保護メガネ
- 換気扇や扇風機
- 消毒用エタノールまたはカビ取り剤
- 古い歯ブラシやスポンジ
- 乾いた布や雑巾
2.消毒用エタノールで拭き取る
 カビを除去する際に最も効果的なのが、消毒用エタノールを使用する方法です。
カビを除去する際に最も効果的なのが、消毒用エタノールを使用する方法です。
スプレーボトルに入れた消毒用エタノールをカビの発生している部分にしっかり吹きかけ、そのまま5~10分ほど放置します。
その後、柔らかい布やキッチンペーパーで優しく拭き取ります。
細かいカビは、もう使用しない歯ブラシなどでこすり落としましょう。
3.乾燥をする
カビを取り除いた後は、押し入れをしっかりと乾燥させることが重要です。
湿気が残っていると、再びカビが発生する原因になります。
押し入れの扉を開けたままにし、エアコンの除湿機能や除湿機を活用すると、効果的に湿気を取り除けます。
エタノールがない場合は重曹やクエン酸も有効
消毒用エタノールが手元にない場合は、重曹やクエン酸を活用する方法も有効です。
特に、小さな子どもやペットがいる家庭では、化学薬品を使わずに掃除ができるため安心です。
重曹を使用する方法
 水500ミリリットルに重曹大さじ1を溶かし、スプレーボトルに入れて重曹スプレーを作りましょう。
水500ミリリットルに重曹大さじ1を溶かし、スプレーボトルに入れて重曹スプレーを作りましょう。
この重曹スプレーをカビが発生している部分に吹きかけます。
そのまま10分ほど放置した後、スポンジや布で優しく拭き取り、仕上げに乾いた布でしっかりと水分を取り除きます。
クエン酸を使用する方法
こちらもクエン水酸スプレーをまずは作成します。
水500ミリリットルにクエン酸小さじ1を溶かし、スプレー容器へ移しましょう。
このクエン酸水スプレーをカビに吹きかけて、15分ほど放置します。
その後、布で拭き取り、押し入れを十分に乾燥させます。
体験しませんか?
押し入れにカビができる原因は?
なぜ押入れにはカビが発生しやすいのでしょうか?
押入れにカビができやすいのは、下記の原因がほとんどです。
- 湿気のこもりやすさ
- 温度が高い
- 収納物の湿気
- 結露が発生しやすい
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
湿気がこもりやすい
 押し入れは、密閉されていて湿気がこもりやすいため、カビが発生しやすいです。
押し入れは、密閉されていて湿気がこもりやすいため、カビが発生しやすいです。
特に梅雨や冬場は、湿度が上がりやすく、カビの発生リスクが高まります。
また、壁と収納物の間に空間がないと、さらに湿気が逃げにくくなるため、注意が必要です。
温度が高い
押入れは扉を閉めて密閉しているため、温度が高く、カビが発生しやすいです。
カビは20~30℃の温度で湿気の高い環境で繁殖しやすいです。
夏場はもちろん、暖房の熱がこもる冬場も、カビの発生条件が揃いやすくなります。
収納物の湿気
布団や衣類などの収納物の水分が、押し入れ内の湿度をさらに高める原因になります。
特に、寝汗を含んだ布団や、湿ったまま収納した衣類は、カビを発生させる大きな要因です。
結露が発生しやすい
 押し入れの壁が外壁に面している場合、冬場に結露が発生することもあります。
押し入れの壁が外壁に面している場合、冬場に結露が発生することもあります。
この結露によって、壁や収納物が湿り、カビの温床になってしまいます。
結露の対策方法は、こちらの記事にて詳しく解説しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
押し入れのカビを予防する方法
押し入れのカビを防ぐためには、湿気対策と通気性の確保が鍵になります。
下記の方法を実践して、カビが発生しにくい環境を作りましょう。
- 定期的に換気を行う
- すのこを敷いて通気性を確保
- 布団や衣類を乾燥させてから収納する
- 除湿剤や新聞紙を活用する
- エアコンや除湿機を活用する
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
定期的に換気を行う
押し入れは定期的に扉を開けて換気を行うことが大切です。
少なくとも週に1回は開け放ち、扇風機やサーキュレーターを使って空気を循環させると、より効果的です。
すのこを敷いて通気性を確保
 押し入れの床にすのこを敷くことで、収納物と床の間に空間を作り、通気性を確保できます。
押し入れの床にすのこを敷くことで、収納物と床の間に空間を作り、通気性を確保できます。
また、すのこは壁に立てかけるように設置すると、さらに空気の流れが良くなります。
布団や衣類を乾燥させてから収納する
収納前に布団や衣類をしっかり乾燥させることが重要です。
特に布団は、定期的に天日干しや布団乾燥機を使用し、湿気を取り除いてから収納しましょう。
除湿剤や新聞紙を活用する
押し入れの湿気を吸収するために、除湿剤や新聞紙を設置するのも効果的です。
新聞紙は、手軽に湿気を吸収できるため、収納物の下に敷いておくと良いでしょう。
エアコンの除湿機能を活用する
梅雨の時期や湿気の多い日は、エアコンの除湿機能を活用して室内全体の湿度を下げるのも効果的です。
ます。
体験しませんか?
ハウスクリーニングはアールクリーニングへ依頼がおすすめ
アールクリーニングは最新の洗浄機器、ならびに技術とアフターサービスで、多くのお客様にリピートをいただいております。
以下では、アールクリーニングの強みを紹介します。
1.清掃技術と品質管理

アールクリーニングは独自の研修制度を採用し、厳しい研修を最後までクリアしたスタッフのみ、お客様のもとへサービスに伺います。
自社の研修施設では、さまざまなメーカーや業務用のエアコン用意。
また、こちらの研修施設では、エアコン以外にも換気扇や水回りの研修も実施しています。
スタッフがいつでも練習できる環境を用意し、作業員のスキルアップを支援しています。
2.安心と実績

アールクリーニングは累計50万件以上の作業実績を誇る、経験豊富なハウスクリーニング専門サービスです。
一つひとつの現場に丁寧に対応してきた結果、Google口コミは1,100件を突破し、平均評価4.7という高い満足度を維持しています。
作業後も「掃除して終わり」ではなく、2週間保証のサポート体制を整えているため、初めての方でも安心してご利用いただけます。
地域密着の姿勢と技術力の高さで、リピート利用や紹介も多いのがアールクリーニングの特徴です。
3.リーズナブルな価格設定
本社をあえて郊外に構え、賃料や駐車場代を抑えるなど、サービスを少しでも低価格で提供するために余計な経費を抑えています。
一般的な相場よりも価格を抑えてサービスが受けられるのもメリットの1つです。
体験しませんか?
アールクリーニングの対応地域一覧
アールクリーニングでは下記の地域でご依頼を承っております。
お住まいのエリアが対象かどうか気になる方は、以下から開いて一度チェックしてみてください。
開いて対応地域を詳しく見る
※以下の各ページではエアコンクリーニングについてご紹介していますが、ハウスクリーニング全般もお電話やメールからご相談を承っております。
東京都
23区全域
千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区
市部
八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 武蔵村山市 / 多摩市 / 稲城市 / 羽村市 / あきる野市 / 西東京市 / 瑞穂町(西多摩郡) / 日の出町(西多摩郡)
埼玉県
さいたま市全域
緑区 / 西区 / 浦和区 / 桜区 / 中央区 / 南区 / 大宮区 / 北区 / 見沼区 /
その他の市町村
川越市 / 川口市 / 所沢市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / 蓮田市 / 吉川市 / ふじみ野市 / 白岡市 / 三芳町(入間郡) / 松伏町(北葛飾郡)
神奈川県
横浜市
鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ケ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 緑区 / 青葉区 / 都筑区 / 港南区 / 旭区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 戸塚区
川崎市全域
川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 宮前区 / 多摩区 / 麻生区
その他の市区・郡部
相模原市緑区 / 相模原市中央区 / 相模原市南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 秦野市 / 厚木市 / 大和市 / 伊勢原市 / 海老名市 / 座間市 / 綾瀬市 / 葉山町(三浦郡) / 寒川町(高座郡) / 愛川町(愛甲郡) / 清川村(愛甲郡)
カビ予防に便利なアイテム
カビの発生を防ぐために、以下のアイテムを活用するとより効果的です。
- 除湿剤
- 防カビスプレー
- すのこ・収納ラック
それぞれのアイテムについて詳しく見ていきましょう。
除湿剤
除湿剤には使い捨てタイプと再利用可能なタイプがあります。
使い捨てタイプは、内部の吸湿成分が飽和すると効果がなくなるため、1~2か月ごとに交換すると効果を持続させられます。
防カビスプレー
防カビスプレーは、カビの繁殖を防ぐ抗菌成分を含んでおり、スプレーするだけで押し入れの内壁や収納物をカビから守れます。
スプレーを使用する際は、押し入れ全体にまんべんなく噴霧し、しっかり乾燥させることが重要です。
すのこ・収納ラック
すのこを敷くことで、収納物と床の間に空間を作り、湿気が逃げやすい環境を作れます。
また、収納ラックを活用することで、布団や衣類を直接押し入れの床に置かず、空間を確保できます。
まとめ
押し入れのカビ対策には、湿気の管理と通気性の確保が重要です。
もしカビが発生してしまった場合は、エタノールや重曹で速やかに除去し、その後しっかり乾燥させることが大切です。
さらに、除湿剤や防カビスプレーを活用することで、長期間清潔な状態を保てます。
日々のちょっとした工夫で、押し入れのカビを防ぎ、大切な収納物を守りましょう!