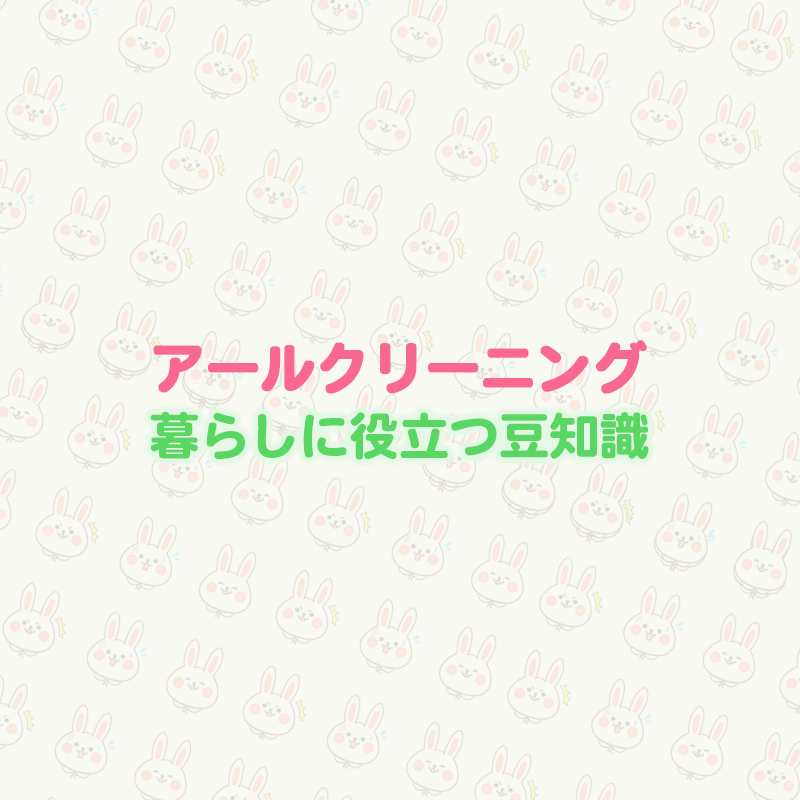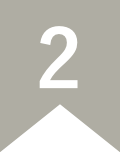寒い季節、暖房の設定温度を20度にしているのに、なんだか寒く感じる…そんな経験はありませんか?
設定温度を上げても快適に感じない原因は、部屋の環境や使い方にあることが多いのです。
この記事では、暖房の20度設定が適温なのか、効率よく部屋を暖める方法、さらに節約術まで詳しく解説します。
寒さに困っている方はぜひ参考にしてください!
30秒で内容を知りたい方はこちらの動画をご覧ください。
暖房の20度は適温?
日本では、暖房の設定温度は20度が目安として認識されていることが多いです。
これは、環境省が提唱する「ウォームビズ」にて20度を提唱していることが大きいです。
環境省が暖房を20度に推奨する理由は以下のとおりです。
- 環境への配慮:暖房の使用量を抑えることで、二酸化炭素排出を削減できる。
- エネルギー節約:設定温度を1度下げるごとに、約10%のエネルギーが節約できる。
- 体感温度を補う方法がある:衣服やカーペットなどで補うことが前提。
参考:環境省公式ホームページ,報道・広報,報道発表一覧,令和3年度,ウォームビズについて
暖房が20度でも寒く感じる原因
暖房の設定温度を20度にしても寒く感じる理由には、次のようなものがあります。
断熱性能の問題
部屋が寒く感じる大きな原因の一つは、断熱性能です。
窓や壁、ドアなどの断熱が不十分だと、室内で温められた空気が外に逃げる一方で、冷気が侵入してしまいます。
窓ガラスがシングルガラスの場合、外気の影響を受けやすく、暖房で温めた空気が窓周辺から冷やされます。
また、壁や床に断熱材が入っていない場合、外部から冷気が伝わりやすくなります。
空気の循環が不十分
 暖房を20度に設定しても寒い場合は、暖かい空気が部屋の上部に溜まっている可能性があります。
暖房を20度に設定しても寒い場合は、暖かい空気が部屋の上部に溜まっている可能性があります。
暖かい空気は軽いため、天井付近に溜まりやすく、足元が冷たいままになることが多いです。
エアコンの風向きが適切でない場合、暖かい空気が一部のエリアに集中してしまいます。
サーキュレーターや扇風機を使うことで、空気を循環させられます。
湿度が低い
 湿度が低いと体感温度が実際の室温よりも低く感じられることがあります。
湿度が低いと体感温度が実際の室温よりも低く感じられることがあります。
これは、乾燥した空気では汗が蒸発しやすくなり、体温が奪われやすいためです。
例えば、室温が20度でも湿度が30%以下になると、15~16度程度の体感温度になってしまいます。
エアコン内部が汚れている

暖房をつけても部屋が暖まらない原因のひとつが、エアコン内部の汚れです。
長期間掃除をしていないエアコン内部には、ホコリやカビが熱交換器やフィルターに付着しています。
このエアコン内部の汚れが空気の流れを妨げ、設定温度通りに部屋を温められなくなることがあります。
「風は出ているのに部屋が暖まらない」「20度にしても寒い」と感じるときは、エアコン内部の洗浄を行うことで、暖房効率が大きく改善するケースが多いです。
体験しませんか?
暖房の適切な設定温度は?
 エアコン暖房の適切な設定温度は、快適さと省エネのバランスを考えることが重要です。
エアコン暖房の適切な設定温度は、快適さと省エネのバランスを考えることが重要です。
暖房の温度設定を適切に行うことで、電気代の節約や健康的な室内環境を保てます。
以下では、具体的な設定温度の目安を詳しく解説します。
快適さを重視する場合:22~24度
快適さを優先する場合、多くの人が心地よいと感じる温度は22~23度です。
この温度設定では、特に暖房使用時に薄着でも過ごしやすく、家族全員がリラックスできる空間を作り出せます。
こんな人におすすめ
22度~24度は以下のような方におすすめの設定温度です。
- 小さな子どもや高齢者がいる家庭(体温調節が難しいため)。
- 寒がりの人や冷え性の人。
節約を重視する場合:20~21度
節約や環境負荷を軽減したい場合、設定温度を20~21度にするのがおすすめです。
この温度は、家庭やオフィスなどで広く推奨されており、エネルギー消費を抑えながら適度に暖かさを感じられます。
こんな人におすすめ
20度~22度は以下のような方におすすめの設定温度です。
- 電気代を抑えたい人。
- 地球環境への配慮を重視する人。
- 暖かい服装やブランケットなどで工夫できる人。
効率的に部屋全体を暖める方法
ここでは、段法を使用して効率的に部屋を均一に暖める方法を紹介します。
風量を調整する
エアコンの風量設定を「自動」にすることで、部屋全体が効率よく均等に暖まります。
風量を手動で設定すると、暖かい空気が偏ってしまうことがあり、結果的に体感温度が下がる原因になります。
効果的な設定方法
効果的な設定方法は以下のとおりです。
- エアコンの風向きを下向きに調整する。
- 冷気がたまりやすい足元を重点的に暖める。
エアコンの自動運転についてはこちらの記事でも解説しています。
サーキュレーターを併用する
 暖房とサーキュレーターを併用することで、エアコンから出る暖かい空気を効率よく部屋全体に循環させられます。
暖房とサーキュレーターを併用することで、エアコンから出る暖かい空気を効率よく部屋全体に循環させられます。
暖かい空気は天井付近に溜まりやすいです。
サーキュレーターを利用することで、この天井付近に留まった空気をを部屋全体に行き渡らせます。
また、サーキュレーターで効率よく設定温度まで達することで、エアコンの消費電力が抑えられ、電気代の節約につながります。
湿度を適切に保つ
暖房を効率よく使うには、湿度管理も大切です。
空気が乾燥すると体感温度が下がり、余計に寒く感じてしまいます。
湿度の推奨レンジは公的基準でも40~70%ですが、湿度を50~60%に保つと快適さが増し、体感温度も少し高くなります。
加湿器を使えば手軽に調整でき、自動運転付きタイプなら常に適した湿度を保てます。
参考:厚生労働省公式サイト,ホーム,政策について,分野別の政策一覧,健康・医療,健康,生活衛生情報のページ,建築物衛生のページ,建築物環境衛生管理基準について
参考:家電 Watch,空調家電,エアコン,加湿すると体感温度がアップ? ダイニチが賢い暖房テクニック紹介
部屋の断熱性を見直す
暖房効率を高めるには、部屋の断熱性を向上させることも重要です。
窓や壁、ドアから冷気が入り込むと、暖房で温めた空気が外に逃げてしまい、設定温度を上げても十分に暖まらないことがあります。
窓に断熱シートを貼ったり、厚手の遮光カーテンを使用することで、外気の影響を軽減できます。
これらの対策を行うことで、エアコンの消費電力を抑えながら快適な室温を保てます。
暖房の節約方法
 寒い季節に欠かせない暖房ですが、使用方法を工夫することで、電気代を節約しながら快適に過ごせます。
寒い季節に欠かせない暖房ですが、使用方法を工夫することで、電気代を節約しながら快適に過ごせます。
ここでは、具体的な節約方法について詳しく解説します。
設定温度を適切に調整
エアコン暖房の設定温度を1度下げるだけで、約10%の電気代を節約できると言われています。
低めの設定温度でも快適に過ごすためには、暖かい衣類やブランケットを活用することが効果的です。
また、電気ストーブやホットカーペットを併用することで、部屋全体の温度を上げずに体感温度を高められます。
タイマー機能を活用
 エアコンのタイマー機能を活用することで、必要な時間だけ運転させて無駄な電力消費を抑えられます。
エアコンのタイマー機能を活用することで、必要な時間だけ運転させて無駄な電力消費を抑えられます。
たとえば、就寝前にタイマーを設定して、就寝中は暖房を切ることで電気代を節約できます。
さらに、朝の起床時間に合わせてタイマーをセットすることで、部屋が寒い時間を最小限に抑えつつ快適な環境を作り出せます。
長時間のつけっぱなしは避け、必要なときに効率よく暖房を使うよう心がけましょう。
適切なフィルター清掃
 エアコンのフィルターにホコリや汚れがたまると、暖房効率が下がり余計な電力を消費する原因となります。
エアコンのフィルターにホコリや汚れがたまると、暖房効率が下がり余計な電力を消費する原因となります。
定期的にフィルターを掃除することで、暖房の効果を最大限に引き出し、電気代を抑えられます。
フィルター掃除の目安として、月に1回程度を目標にしましょう。
掃除機や水洗いを活用してホコリを取り除き、完全に乾燥させてから再び設置することで、暖房効率を維持できます。
暖房器具を併用する
エアコンだけに頼らず、電気毛布やホットカーペット、湯たんぽなどの暖房器具を併用することで電気代を抑えられます。
これらの暖房器具はエアコンと比べて消費電力が少なく、ピンポイントで暖かさを感じられるため、省エネに最適です。
たとえば、電気毛布を使用している間はエアコンの設定温度を低めにするなど、工夫することで暖房費をさらに削減できます。
エアコンの徹底洗浄はアールクリーニングへお任せください!

アールクリーニングは、エアコン洗浄の専門業者として最先端の洗浄機器、ならびに技術とアフターサービスで、多くのお客様にリピートをいただいております。
アールクリーニングのエアコン分解洗浄は、フィルターやファン、熱交換器などの自分では手が届きにくい部分もキレイにします。
以下では、アールクリーニングの強みを紹介します。
清掃技術と品質管理

アールクリーニングでは、自社独自の技術・マナー研修制度により、合格したスタッフのみが現場に出ます。
本格的な研修施設には、さまざまなメーカーのエアコン実機に加え、換気扇や水回りも配置しています。
繰り返し練習できる環境があるからこそ、どのスタッフがお伺いしても高品質な作業を提供しています。
安心と実績

アールクリーニングの作業実績は50万件以上!
その中でもエアコンクリーニングはダントツの一番人気のメニューです。
また、アールクリーニングは、Google口コミ 1,100件以上で★4.7 の高評価を誇り、多くのお客様から
「新品のようにとっても綺麗になりました」
「丁寧な説明とお掃除で気持ちもスッキリしました!」
「さすがプロ!見事!また利用したい」
など、たくさんの嬉しい声も日々いただいております!
清掃作業後もアフターサービスがあるため、安心してご利用いただけます。
万全のサポート体制
アールクリーニングでは自社コールセンターを完備し、迅速なお客様対応を実現しています。
また、清掃作業後にトラブルが発生した場合でも、作業後2週間まで保証対応。
アフターフォローまで万全の体制でサポートいたします。
体験しませんか?
アールクリーニングの対応地域一覧
アールクリーニングでは下記の地域でエアコンクリーニングを行っております。
お住まいのエリアが対象かどうか気になる方は、以下から開いて一度チェックしてみてください。
開いて対応地域を詳しく見る
東京都
23区全域
千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区
市部
八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 武蔵村山市 / 多摩市 / 稲城市 / 羽村市 / あきる野市 / 西東京市 / 瑞穂町(西多摩郡) / 日の出町(西多摩郡)
埼玉県
さいたま市全域
緑区 / 西区 / 浦和区 / 桜区 / 中央区 / 南区 / 大宮区 / 北区 / 見沼区 /
その他の市町村
川越市 / 川口市 / 所沢市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / 蓮田市 / 吉川市 / ふじみ野市 / 白岡市 / 三芳町(入間郡) / 松伏町(北葛飾郡)
神奈川県
横浜市
鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ケ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 緑区 / 青葉区 / 都筑区 / 港南区 / 旭区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 戸塚区
川崎市全域
川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 宮前区 / 多摩区 / 麻生区
その他の市区・郡部
相模原市緑区 / 相模原市中央区 / 相模原市南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 秦野市 / 厚木市 / 大和市 / 伊勢原市 / 海老名市 / 座間市 / 綾瀬市 / 葉山町(三浦郡) / 寒川町(高座郡) / 愛川町(愛甲郡) / 清川村(愛甲郡)
暖房を使用する際の注意点
 暖房を正しく使用することで、快適な室内環境を保ちながら健康にも配慮できます。
暖房を正しく使用することで、快適な室内環境を保ちながら健康にも配慮できます。
ここでは、暖房使用時に注意すべきポイントを解説します。
乾燥対策をする
 暖房を使用すると室内の湿度が低下し、空気が乾燥しやすくなります。
暖房を使用すると室内の湿度が低下し、空気が乾燥しやすくなります。
乾燥した空気は、肌荒れや喉の痛み、風邪などの体調不良を引き起こす原因となります。
そのため、暖房を使用する際には適切な湿度管理が欠かせません。
加湿器を使って湿度を50~60%に保つと、体感温度が上がり暖房効率も向上します。
加湿器がない場合は、濡れタオルを部屋に干したり、室内に洗濯物を干すことで簡単に湿度を補えます。
定期的な換気を行う
暖房を使用していると室内の空気がこもりやすくなります。
こもった空気は二酸化炭素濃度を高め、頭痛や眠気の原因になることがあります。
これを防ぐために、1~2時間に一度、窓を開けて換気を行うことが大切です。
換気をする際は、短時間で効率よく空気を入れ替えるために、対角線上の窓を開ける「クロス換気」を実施しましょう。
新鮮な空気を取り入れることで、室内環境がリフレッシュされ、健康にも良い影響を与えます。
過度な設定温度にしない
設定温度を高くしすぎると、電気代がかさむだけでなく、外気温との差が大きくなり体調を崩す原因になります。
特に、室温と外気温の差が10度以上になると、室外に出たときに体が温度差に適応できず、血圧が急激に変化することがあります。
設定温度は20~23度を目安に調整し、過度に高い温度を避けましょう。
また、暖かい服装や保温グッズを活用することで、無理のない温度設定でも快適に過ごせます。
まとめ
暖房の設定温度20度が寒く感じる原因は、部屋の環境や使い方にあることが多いです。
本記事で紹介した効率的な暖房の使い方や節約術を取り入れて、快適に冬を過ごしましょう。
-
- 断熱や湿度管理をして、体感温度を上げる。
- サーキュレーターや加湿器を活用して効率よく暖める。
- 設定温度は20~23度を目安に調整する。
- 適切な節約術で、暖房費を抑えながら快適さを保つ。
この記事を参考に、寒い冬を乗り越えるための暖房の使い方を見直してみてはいかがでしょうか?